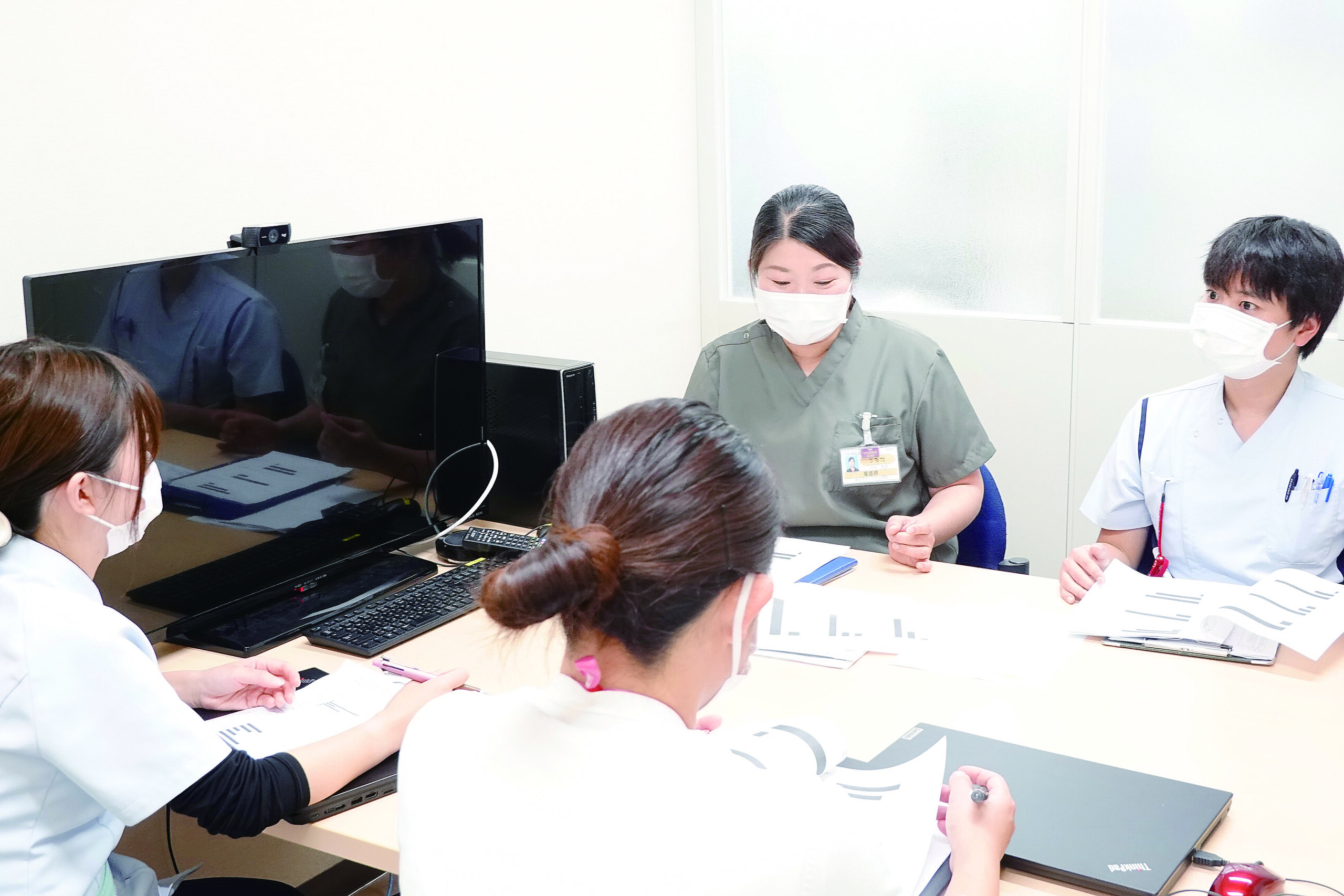私が勤務する鶴川サナトリウム病院は、認知症に関する詳しい診断、行動・心理症状(BPSD)や身体合併症への対応、専門医療相談などを行う「認知症疾患医療センター」として、かかりつけ医や介護・福祉施設、地方自治体とも連携し、認知症の方やその家族に適切な専門医療を提供する役割を担っています。
私が行なっている日々の臨床検査業務には、採血や心電図、超音波などさまざまなものがありますが、その一つひとつが検査用のベッドへの移動、採血のために腕を出していただくことなど、患者さまの協力が必要です。しかし、認知症の患者さまの中には指示が通りにくい方や、不安から警戒心が強い方など、日々の対応に苦労していました。検査技師として、患者さまが安全に検査を受けるにはどうすれば良いか、認知症の症状や行動の背景にあるものを知り、医学的根拠に基づいた適切な対応が必要だと考え、臨床衛生検査技師会の認定認知症領域検査技師資格を目指すことにしました。
実は勉強はもともと得意な方ではありません。資格取得のために勉強することは大変でしたが、学んだことを実践して良い結果が得られたときや、患者さまからの「ありがとう」が大きなモチベーションとなって頑張れたと思います。そして、苦労しながらではありましたが、資格を取得することができました。
資格取得後は、患者さまの病態(病気の状態)が把握できるようになり、認知症の種類に応じた対応が可能になったと感じます。特に幻視や幻聴の症状がある患者さまに対して困惑することもあったのですが、現在は自分が落ち着いた対応をすることで、患者さまも比較的スムーズに検査を受けていただいていると思います。